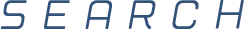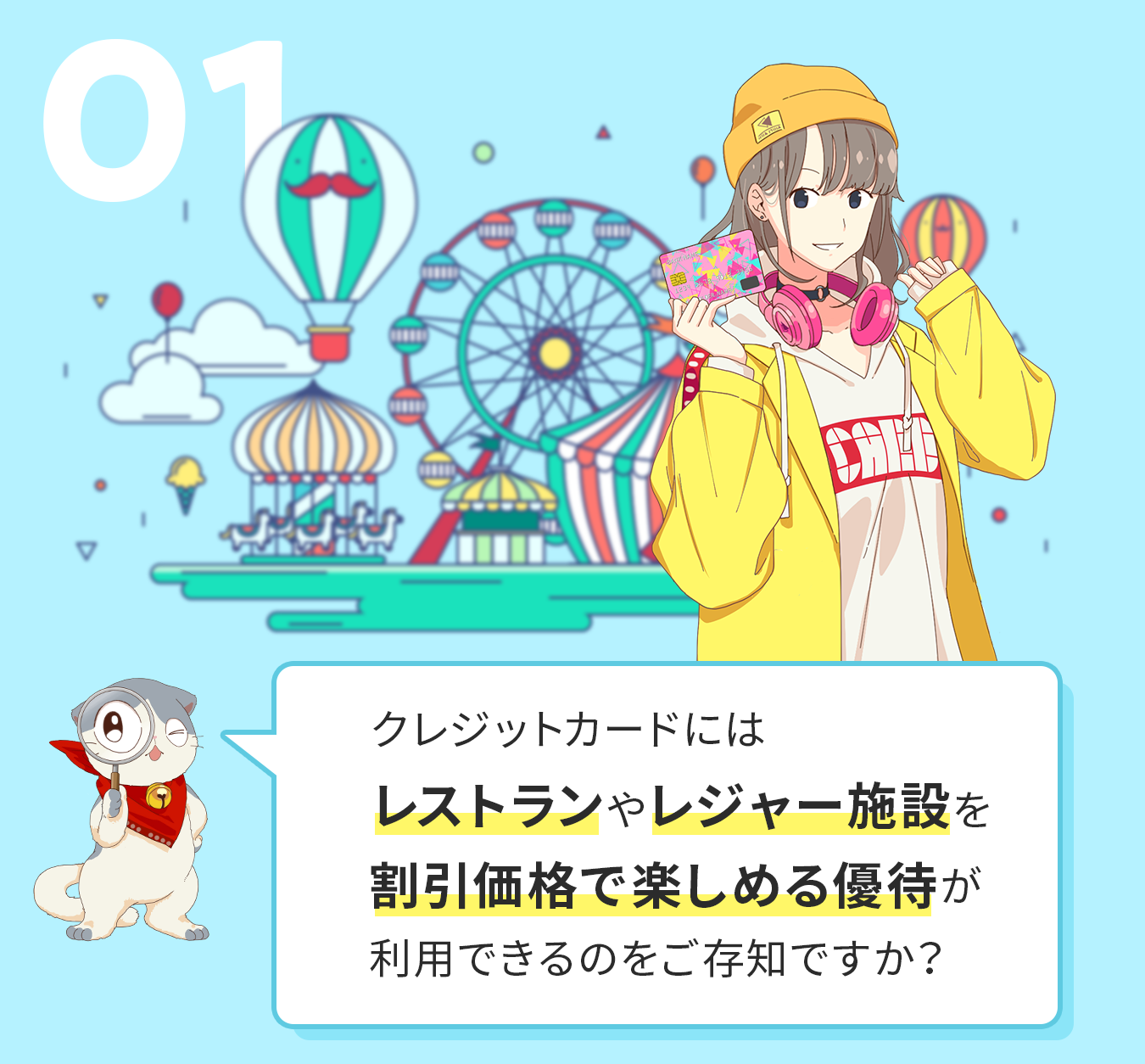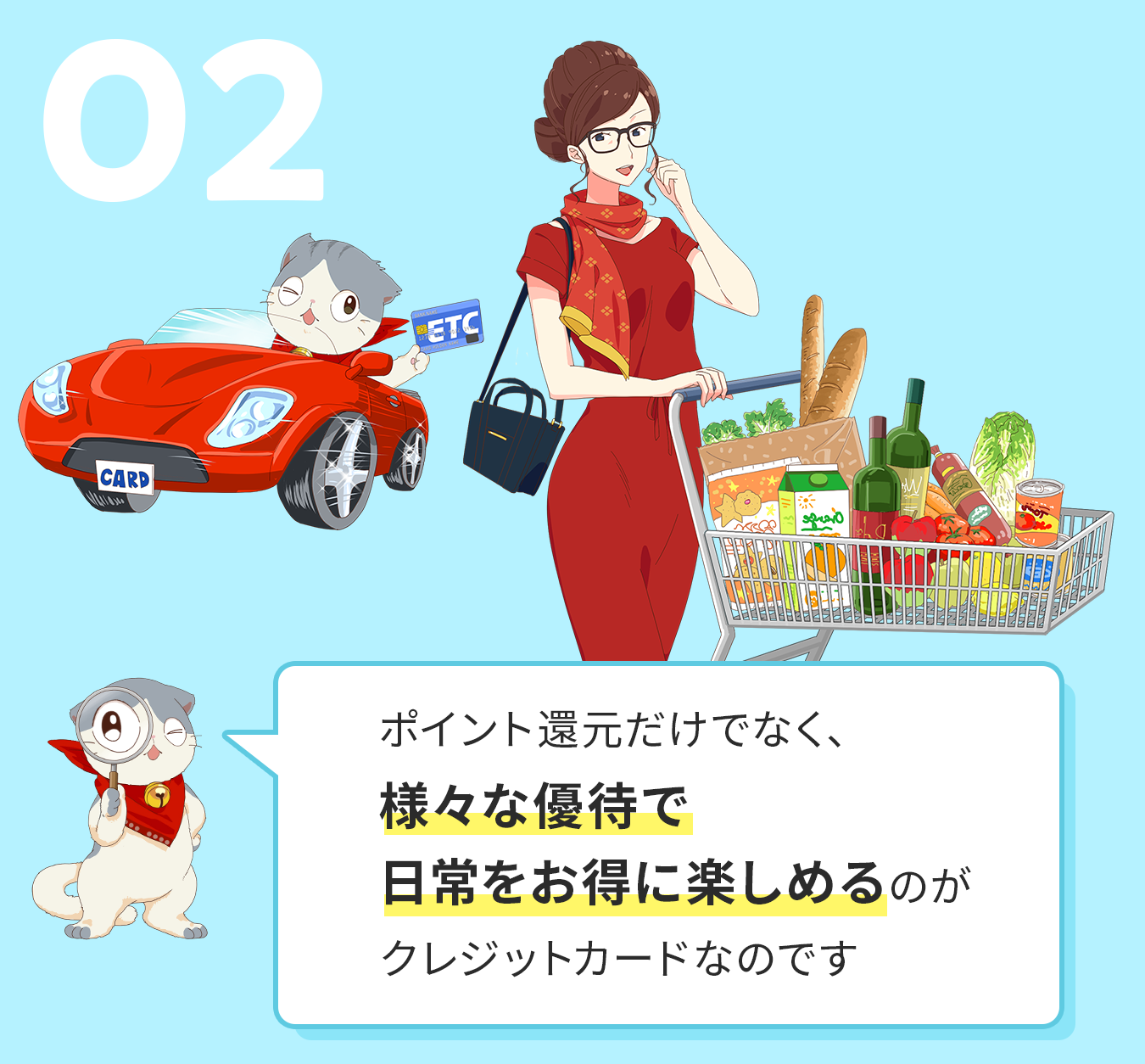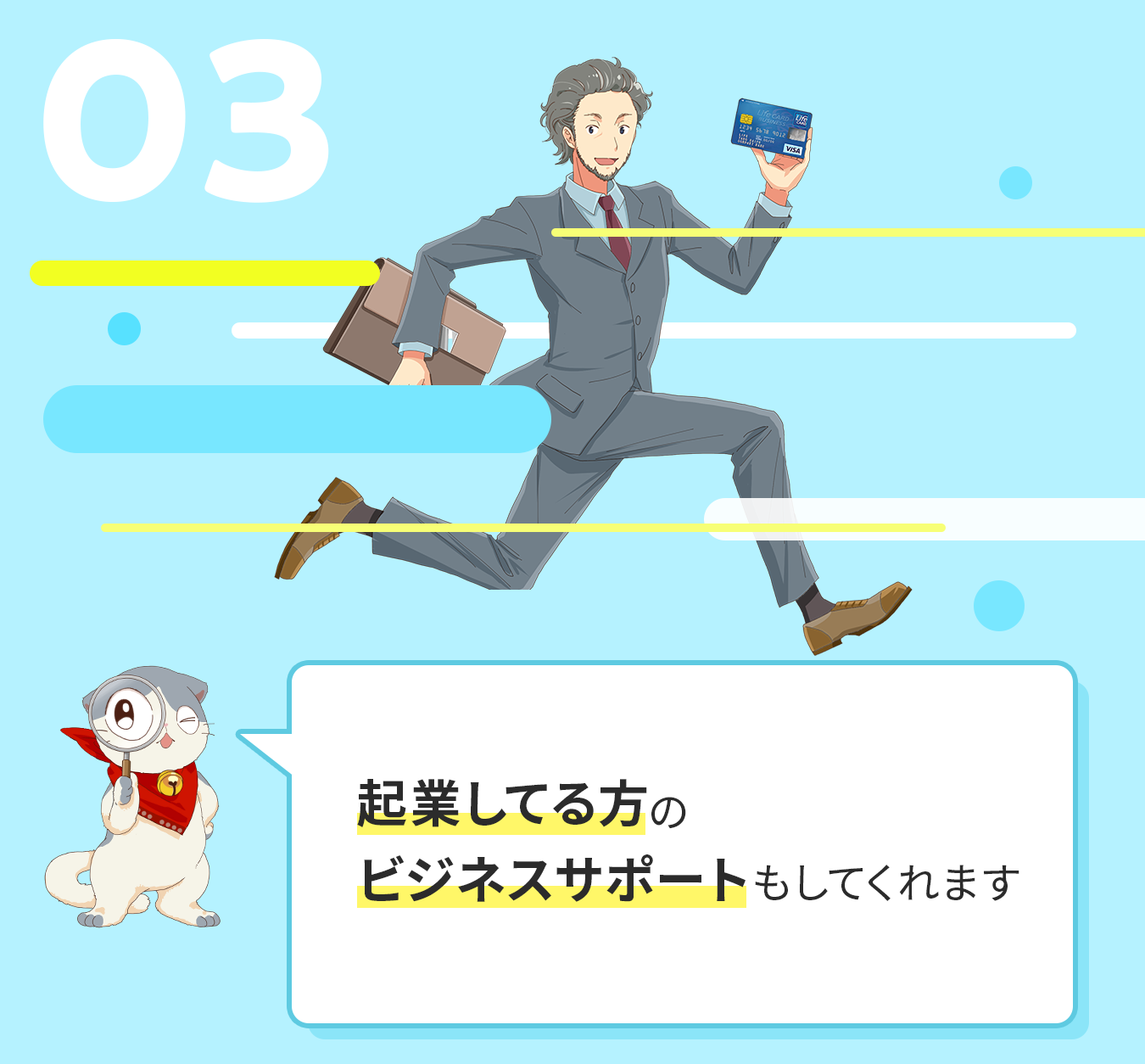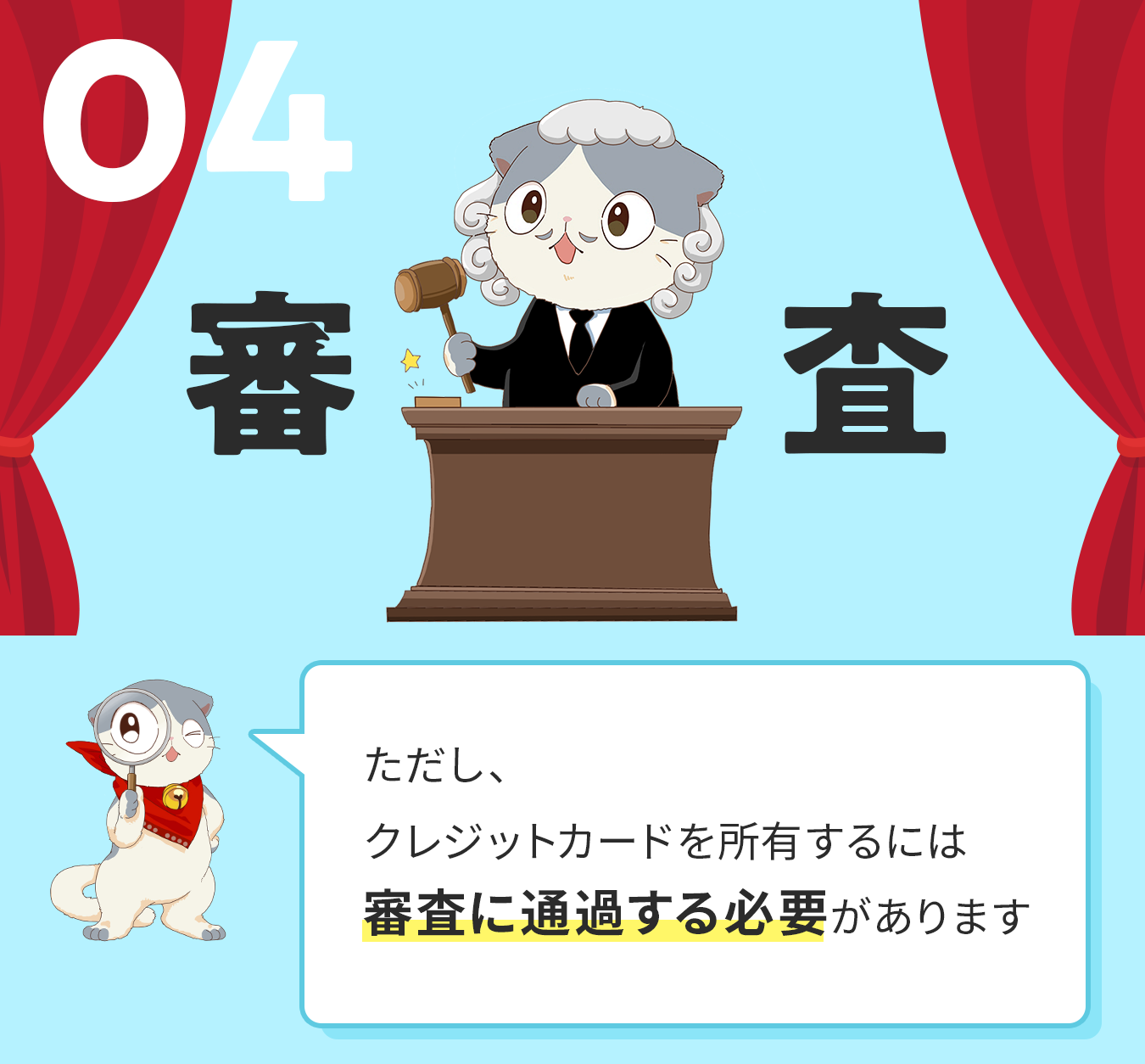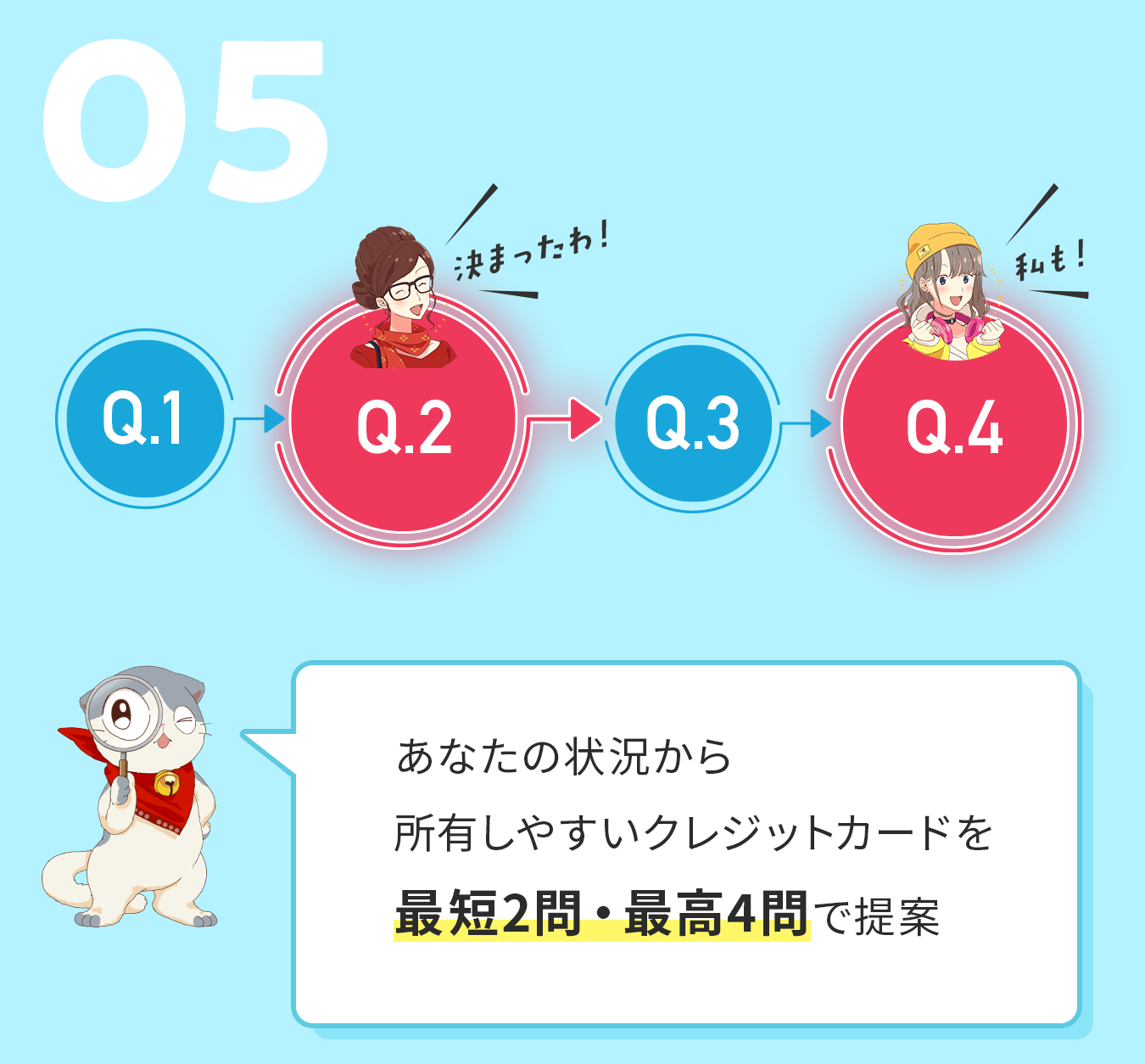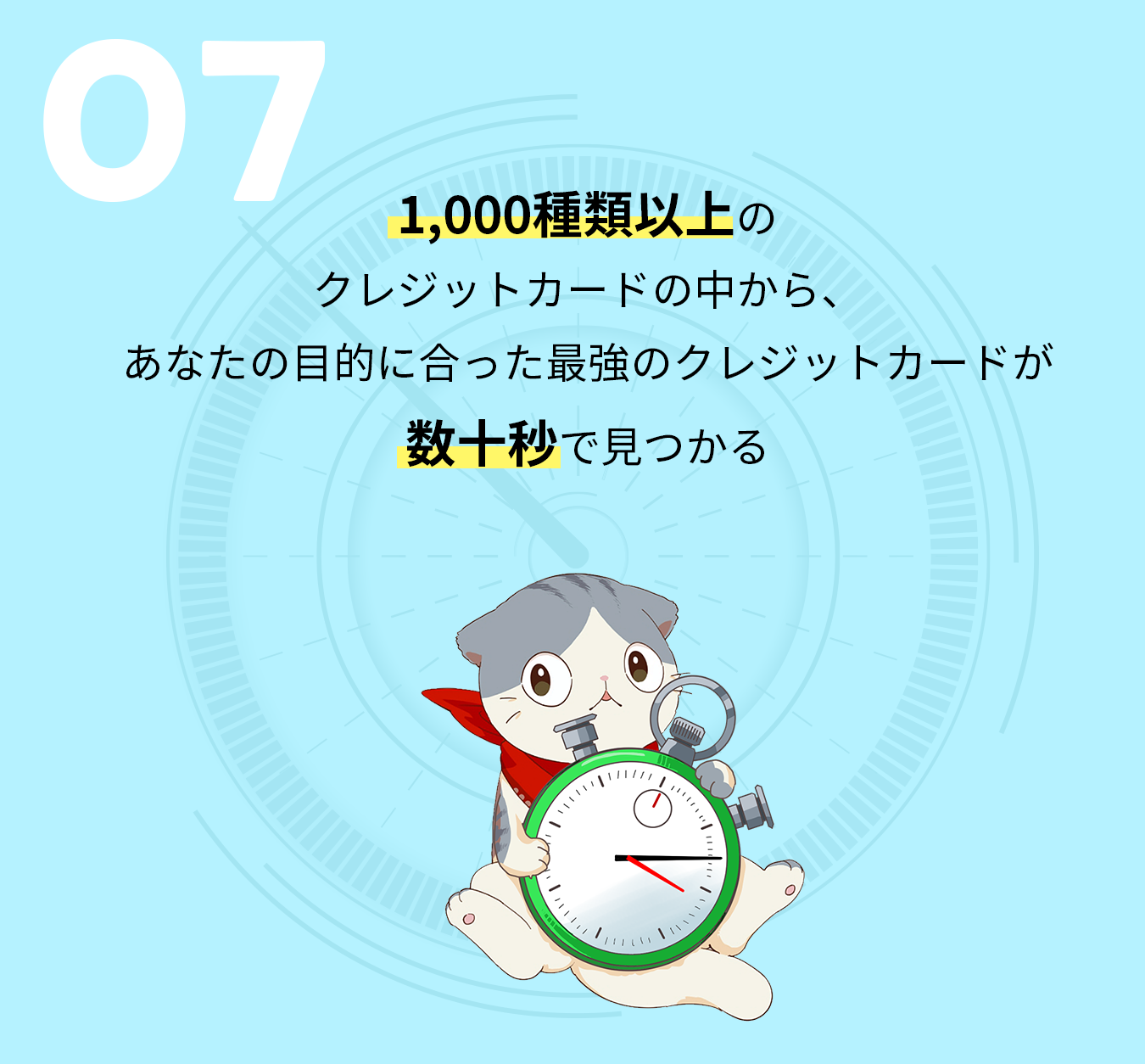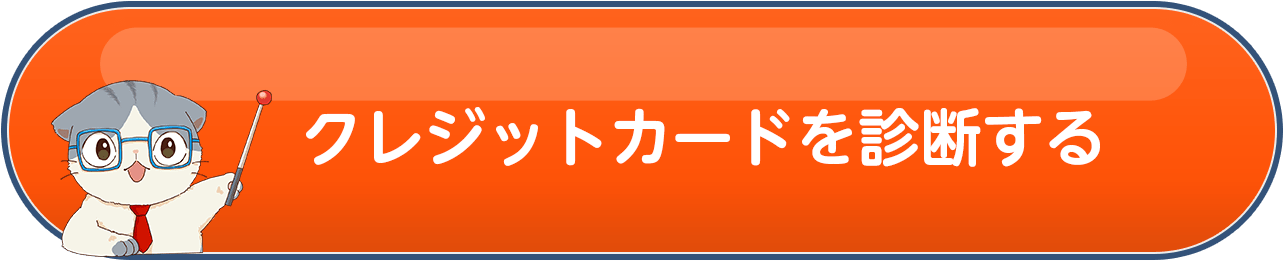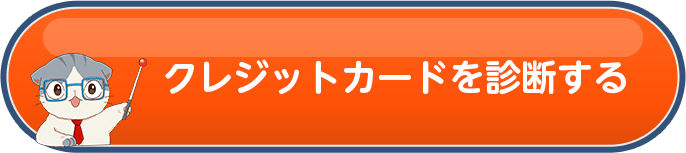スマホ決済
LINE Pay(ラインペイ)不正利用補償!対象や補償期間・額を要確認

投稿日時:2018.07.23
LINE Payのようなモバイル決済サービスを利用する上で気になるのが、オンライン上でのアカウント情報の盗難や不正ログインなどによる不正利用です。
プリペイド式のLINE Payでは万が一悪意のある第三者の手に情報が渡ってしまった場合、残高がある限り容易に不正利用されてしまいかねません。
そこでLINE Payでは、そうした不正利用に対してしっかりと不正利用補償制度を設けています。トラブル発生時に頼りになるLINE Payの不正利用補償制度について、ここでは詳しく解説していきましょう。
不正利用被害をしっかりカバー!LINE Pay(ラインペイ)の不正利用補償制度
LINE Payの不正利用補償制度は、文字通りLINE Payのアカウントを悪用した不正利用によって被害が生じた場合に、その損害を補償する制度です。
LINE Payでは2015年2月よりこの不正利用補償制度が導入され、不正利用に対してより強固に利用者を守る体制を整えています。
アカウント情報特定による不正ログインも補償!不正利用補償適用事例
まずは、LINE Payの不正利用補償制度の適用対象となる事例を確認しておきましょう。
- 端末の紛失・盗難により第三者にLINE Payにログインされ金銭移動が行われた場合
- LINE及びLINE Payのログイン情報が第三者に特定された結果、他の端末からの不正ログインにより金銭移動が行われた場合
- 第三者によるアカウントへの不正ログインにより、LINE Payアカウントから本人以外への送金依頼から金銭移動が行われた場合
LINE Payの不正利用補償の対象となるのは、主に上記のようなケースです。
LINE Payのようなモバイルタイプの決済サービスは、自分自身に落ち度がなく、自覚できない状態でも情報を特定され、不正利用が起きてしまう可能性があるというのが怖いところですよね。
特にLINE PayではLINEの友達同士で送金が行える独自のサービスを取り扱っているので、不正利用被害に友人を巻き込んでしまうリスクがゼロではないというデメリットがあります。
利用者本人に過失アリのケースはNG!不正利用補償制度適用外の事例
実際に不正利用に遭い、損害が出てしまっているにも関わらず、不正利用補償制度の適用外となってしまうケースというのもあります。
- アカウント所持者本人が故意に金銭移動を行った場合
- LINE及びLINE Payのログイン情報を自ら他人に教えたり公開するなどアカウント所持者本人に重大な過失が認められる場合
- LINE Pay利用規約および法令に違反する行為が認められた場合
このように、アカウント所持者、つまり利用者本人に不正利用につながるような行為、あるいは明らかな過失が認められたケースでは、不正利用補償は受けられなくなってしまうので注意が必要です。
例えば家族や友人が相手だと、ついアカウント情報やログイン情報を教えてしまうこともあるかもしれませんが、その情報が何らかの形で他人に知れて不正利用につながってしまうということもあり得ないとは言えません。
LINE Payでの決済やアカウント情報・ログイン情報は、お金のやり取りにかかわる重大な情報です。万が一不正利用被害に遭ってしまったときにもきちんと補償が受けられるように、その情報の重要性を正しく認識し適切に取り扱うように心がけましょう。
補償期間は不正利用発生から31日間!早急に対応すべし
不正利用補償制度を利用する上で最も気を付けてほしいのが、必ず補償期間のうちに対応するということです。
LINE Payの不正利用補償制度の補償期間は、LINE Pay運営が不正利用被害の報告を受付した日の30日前から受付当日までの31日間となっています。
つまり、31日より以前に発生した不正利用被害に対しては、上記の適用事例に該当しても補償を受けることができないのです。
したがって、LINE Payで不正利用被害が発覚したら、なるべく早く手を打つ必要があります。
LINE Payの利用履歴はメインメニューから随時確認することができますし、決済時にはLINE Pay公式アカウントから決済内訳のメッセージが送られてきます。そうした利用履歴情報を確実にチェックして、不審な決済を見逃さないようにしましょう。
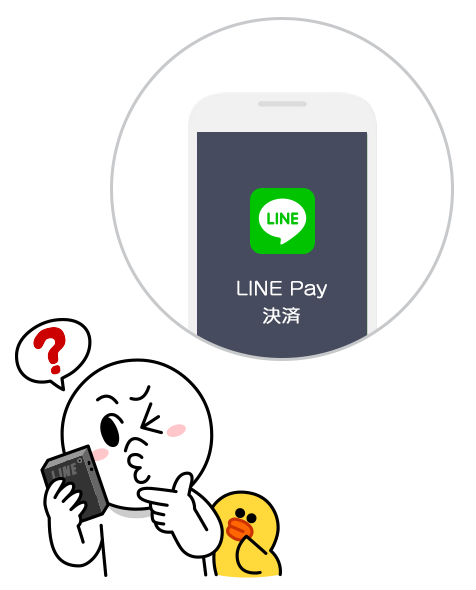
また、スマホを紛失してしまうとLINE Payの利用履歴は当然、確認できなくなります。その場合には、不正利用を未然に防ぐために、早急にLINE Payのアカウントを停止することが重要です。
補償限度額は原則10万円!状況次第で個別に限度額引き上げもあり
LINE Payの補償額は、アカウントの状態によって異なります。まずLINE Pay登録当初に取得できるLINE Cashアカウントの場合は、1事故につき原則10万円限度となります。
これは、LINE Cashアカウントの月間利用額自体が10万円限度となっているからです。
一方で、LINE Payに所定の銀行口座を登録して本人確認を行うことで取得できる、LINE Moneyアカウントのほうは、月間利用限度額が100万円まで跳ね上がります。そうなると、不正利用による被害額が10万円を超えてしまう可能性は十分にありますよね。
したがって、LINE Moneyアカウントの利用者に対しては、損害額が10万円を超えていれば利用状況や警察による捜査結果などを踏まえて補償限度額の引き上げを個別に検討するという形で対応することになります。
なお、LINE Cashアカウントのほうでも、何らかの原因で損害額が10万円を超えてしまった場合には、金額に応じて補償が受けられる可能性があります。ただしこのケースでは10万円超過分の補償は不正利用補償制度とは別に、LINEもしくはLINE Pay運営によって補償が行われるという形になります。
不正利用被害発覚!LINE Payへの申請方法
不正利用が発覚した場合、LINE Payへの申請はLINEアプリ内の問題報告フォームから行うことになります。その際には、可能であれば不正利用被害を受けたことがわかる利用履歴などをスクリーンショットの形式で添付しましょう。

また、不正利用被害に遭ったことを証明するために、事前に警察への届け出が必要となります。
二度手間にならないよう、あらかじめ警察に届け出を済ませてから不正利用被害の申請を行うことをおすすめします。
LINE Pay(ラインペイ)の安全対策!カード情報や銀行口座情報は全て暗号化されている
ここでLINEが行っている安全への対策を何点がご紹介しておきましょう。これをお読み頂ければ、安心してLINE Payを利用する事ができるでしょう。
まず、LINE PayではLINEのパスワードとは別のパスワードの登録が必要となり、送金や決済などには必ずパスワード入力が必要となります。
更に、パソコンやタブレットからLINE Payで商品を購入する際、スマホでの支払い承認が必要な事から、第三者の遠隔操作を未然に防ぐ事もできます。
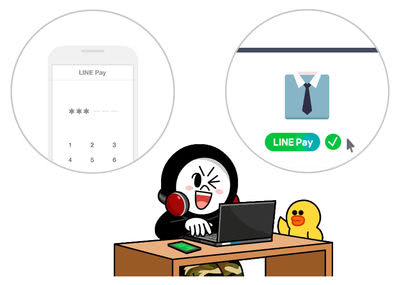
iPhoneをご利用の方なら、指紋認証でのパスワード照会にも対応してますので、更に安心ですね。
カード情報や銀行口座情報は全て暗号化されている
その他にもLINEに登録したクレジットカード情報や銀行口座などの情報は全て暗号化されて保管されます。

支払い先の店舗や送金先などにも一切情報は伝わりません。更に、24時間365日のモニタリング体制が取られていて、不正な動きを行うアカウントを検知してくれるなどの対策も取られてますよ。
万が一のリスクにしっかり対応!LINE Pay(ラインペイ)の不正利用補償制度
LINE Payに限らず、電子マネーやクレジットカードのような決済にかかわるサービスを利用する上では、不正利用のリスクがつきものです。近年は情報盗難の手口も巧妙化しており、自衛するにも限界があります。
だからこそ、こうしてしっかりと不正利用補償制度が確立されているというのは頼もしく感じられますよね。
万が一、不正利用被害に遭ってしまった場合にも確実に補償が受けられるよう、日ごろからアカウントやログイン情報の管理には気を付けるように心がけましょう。